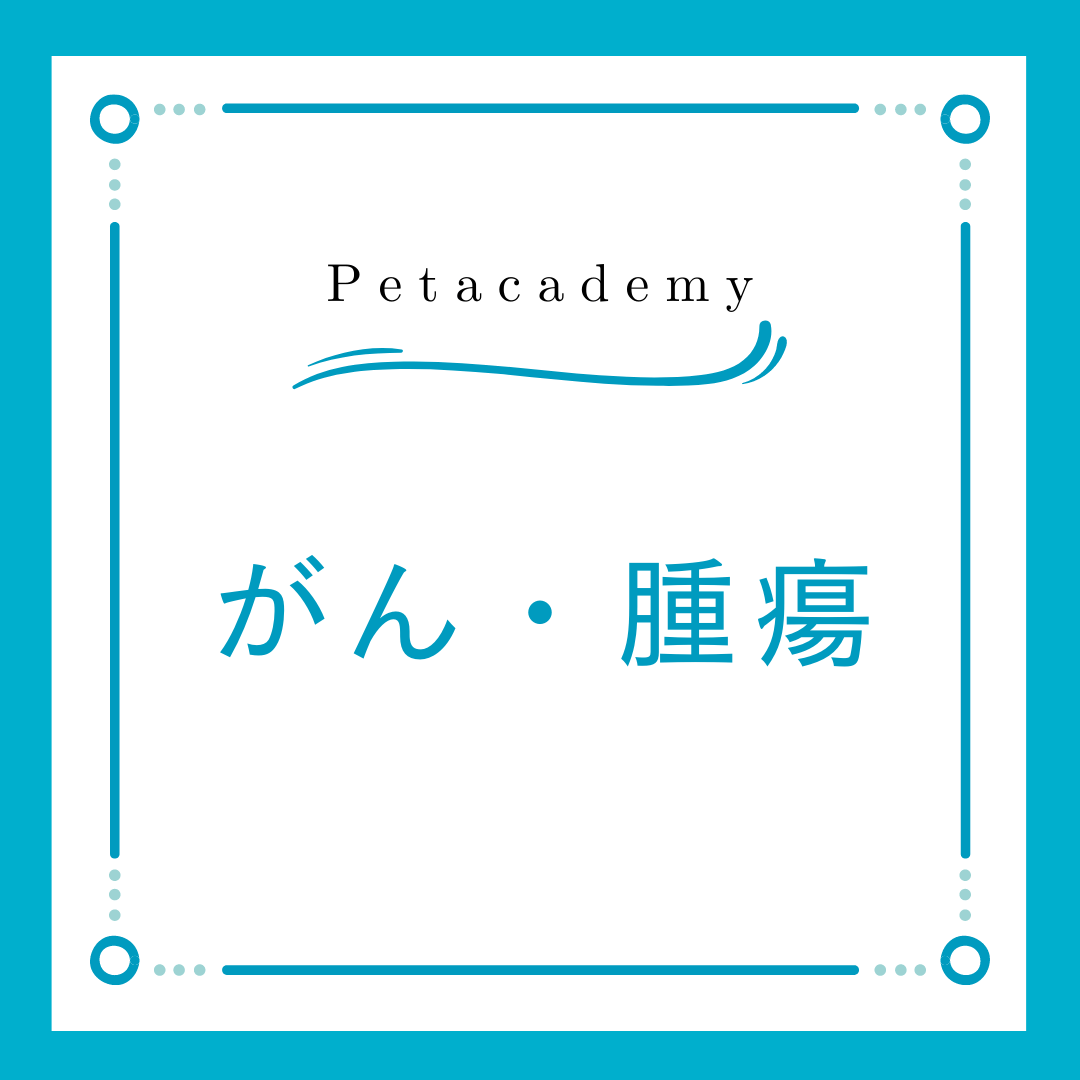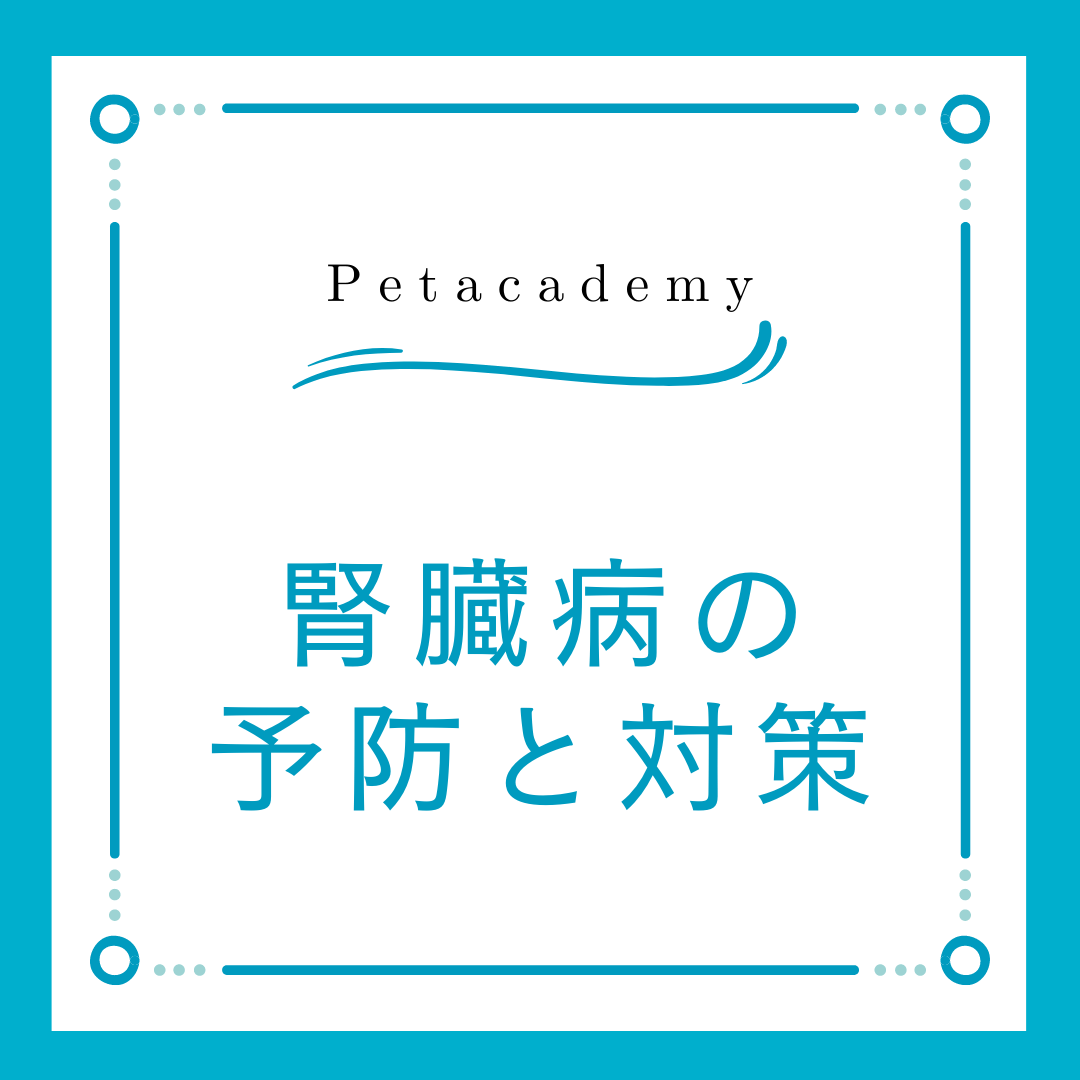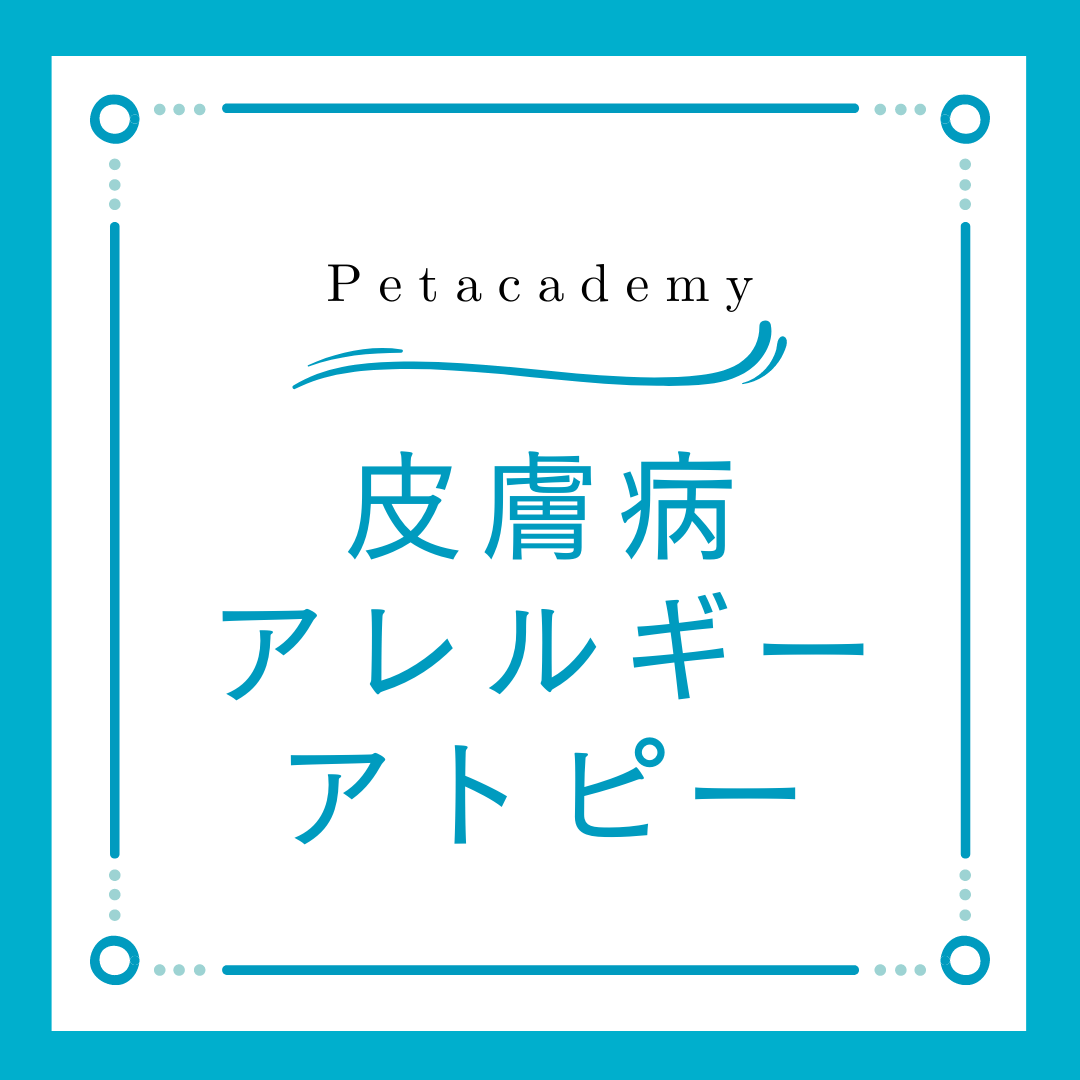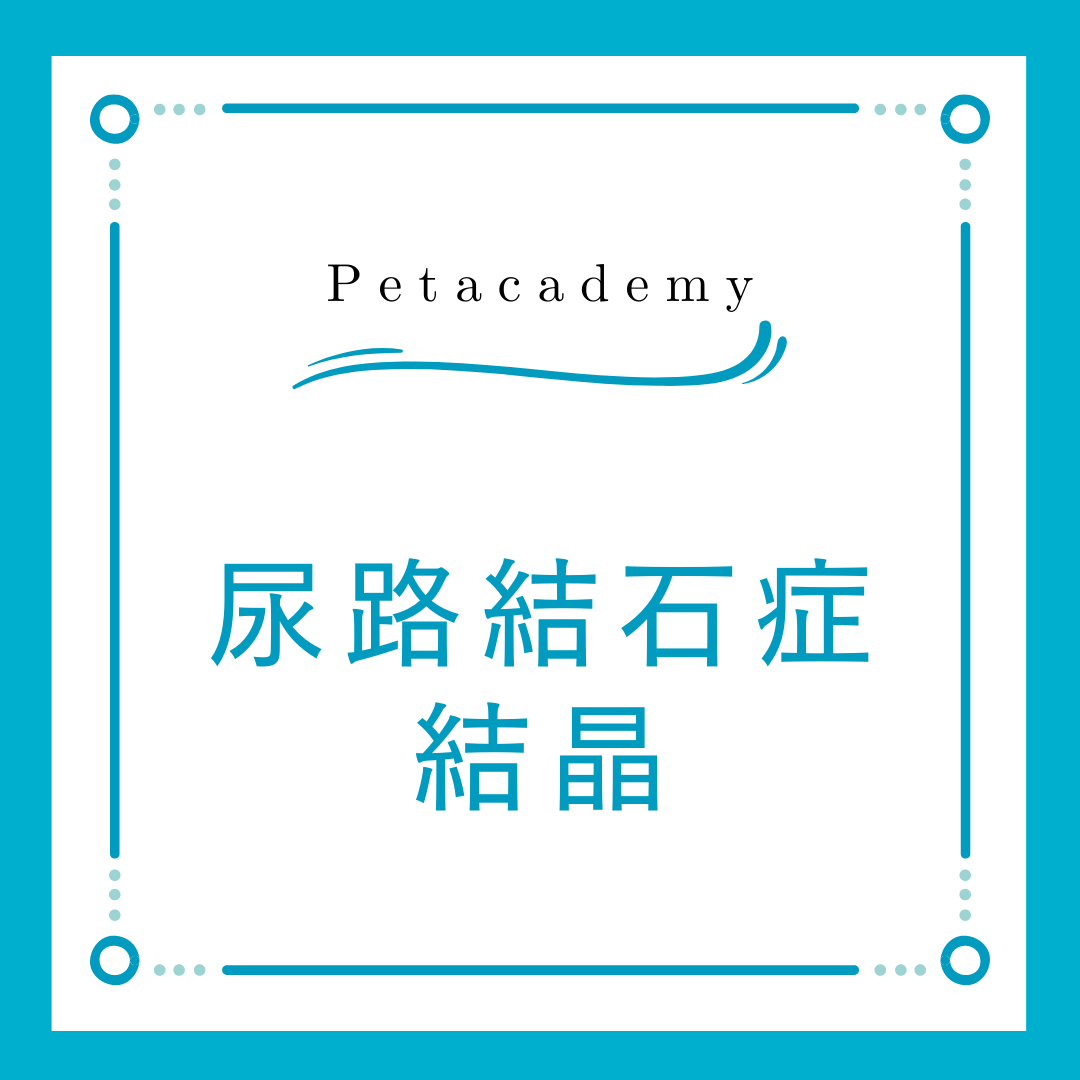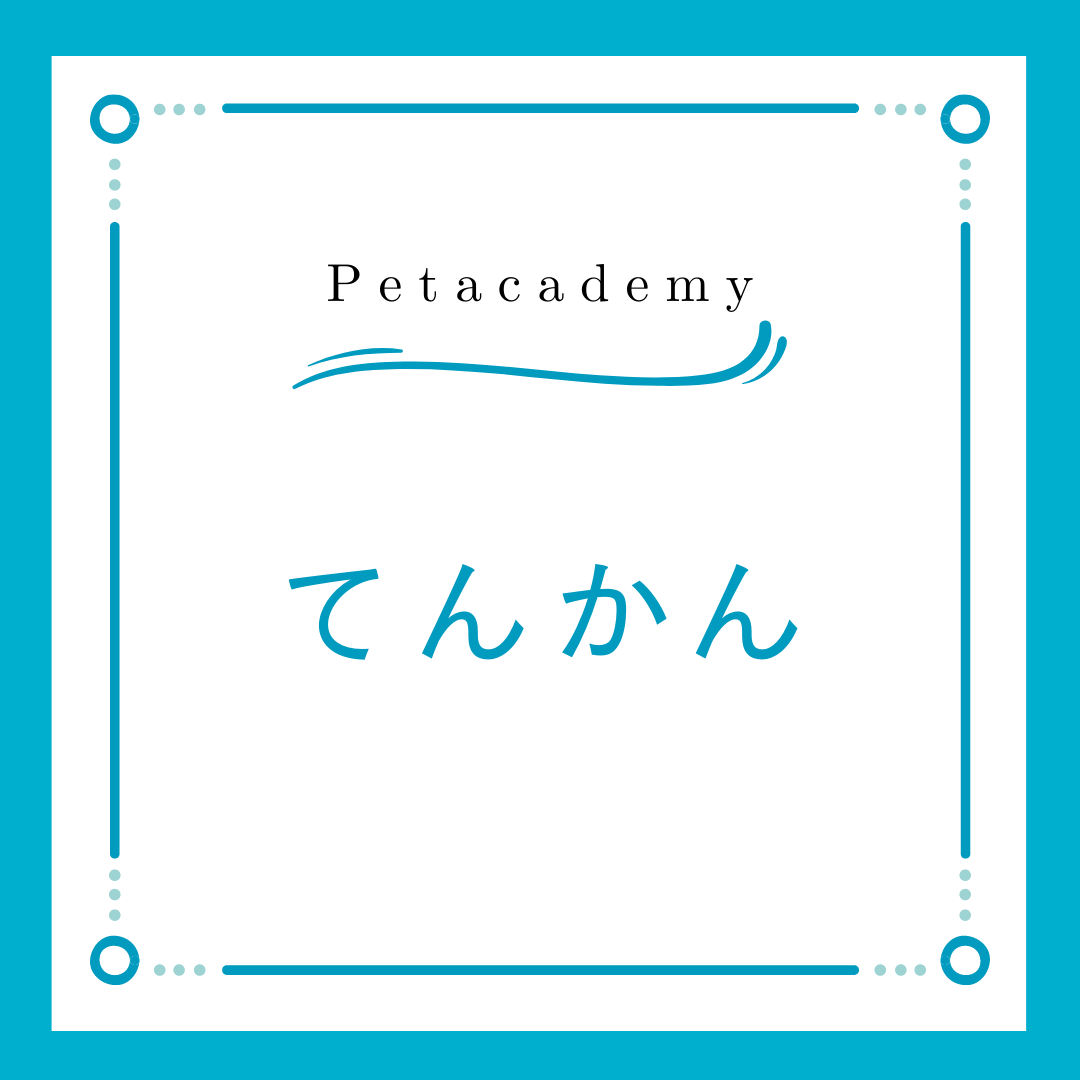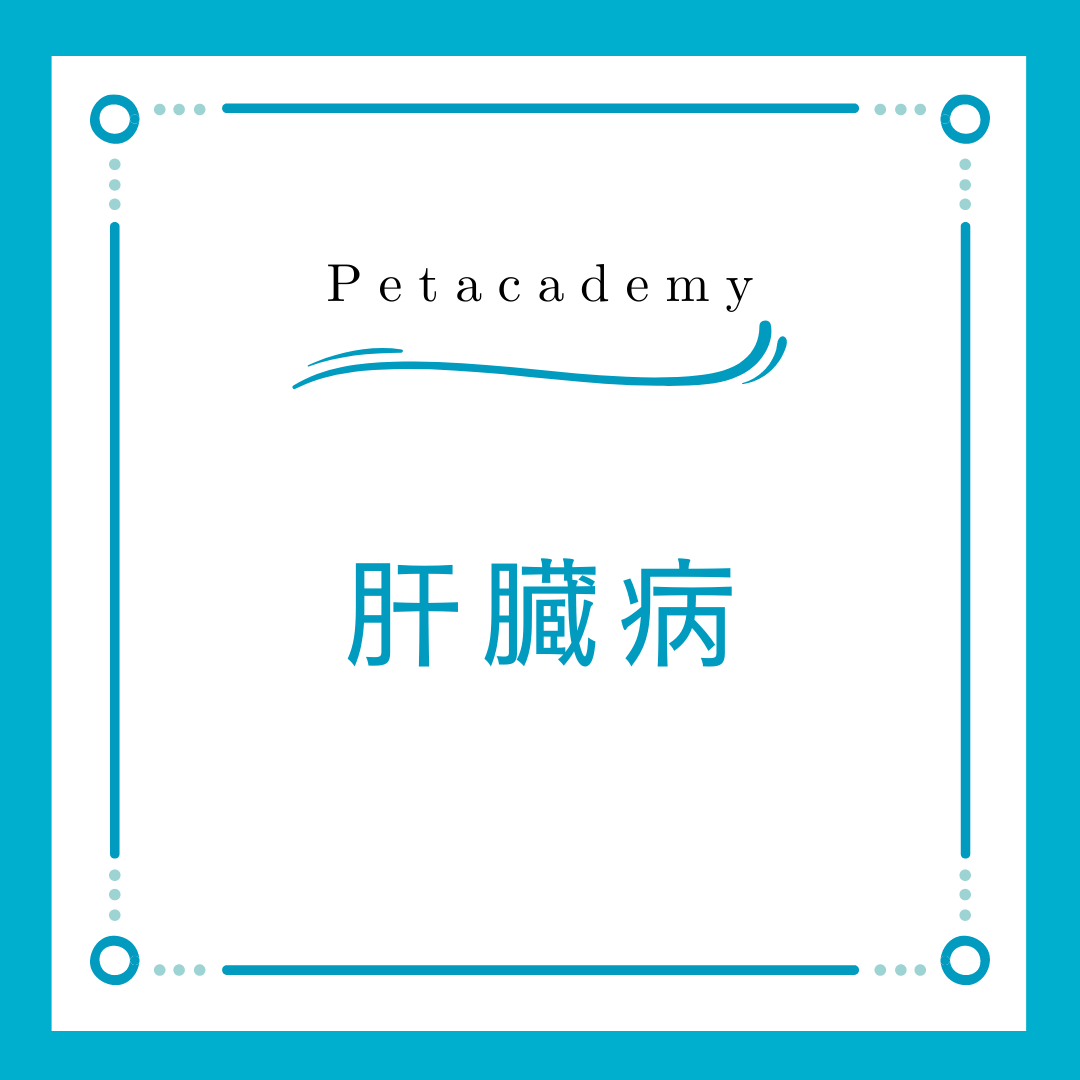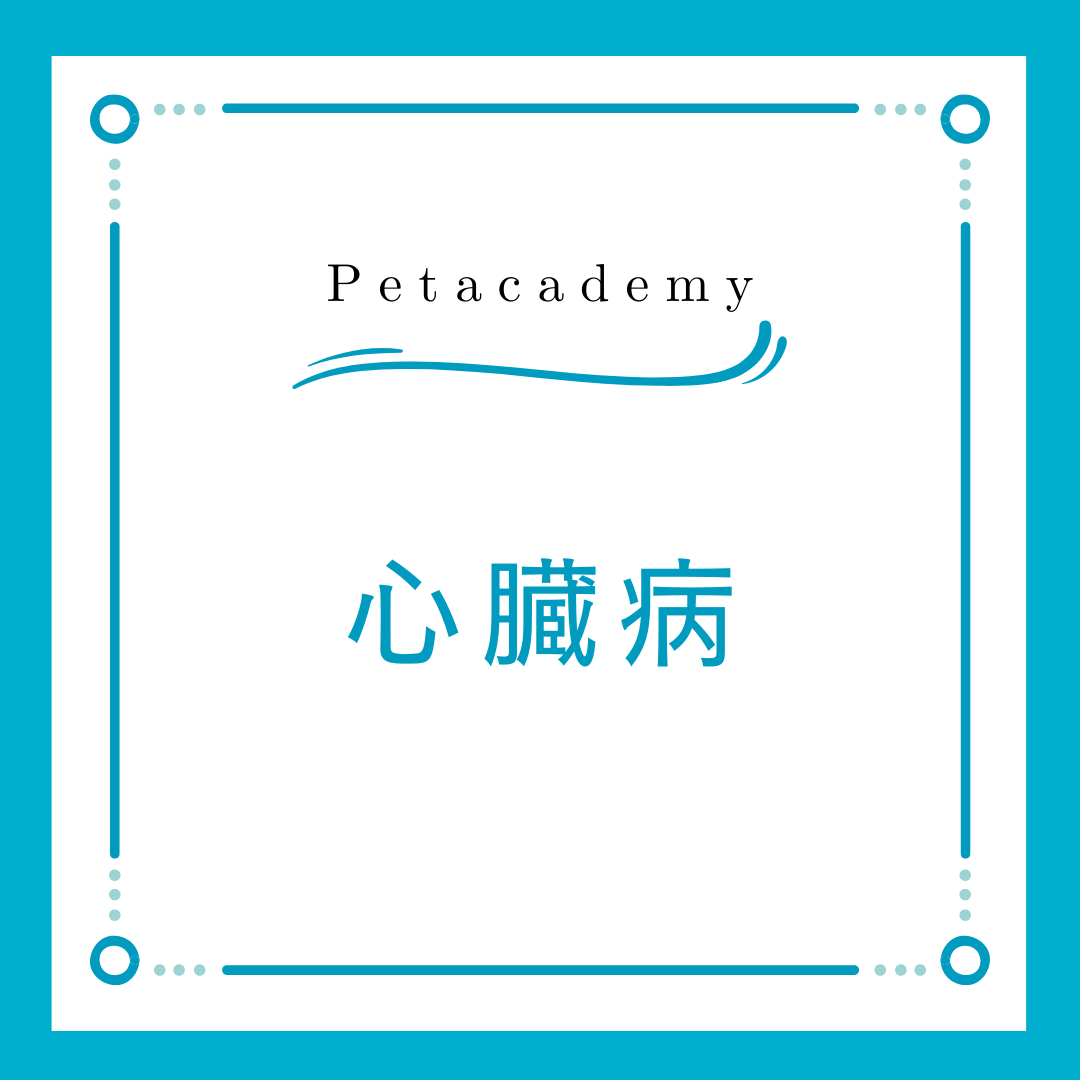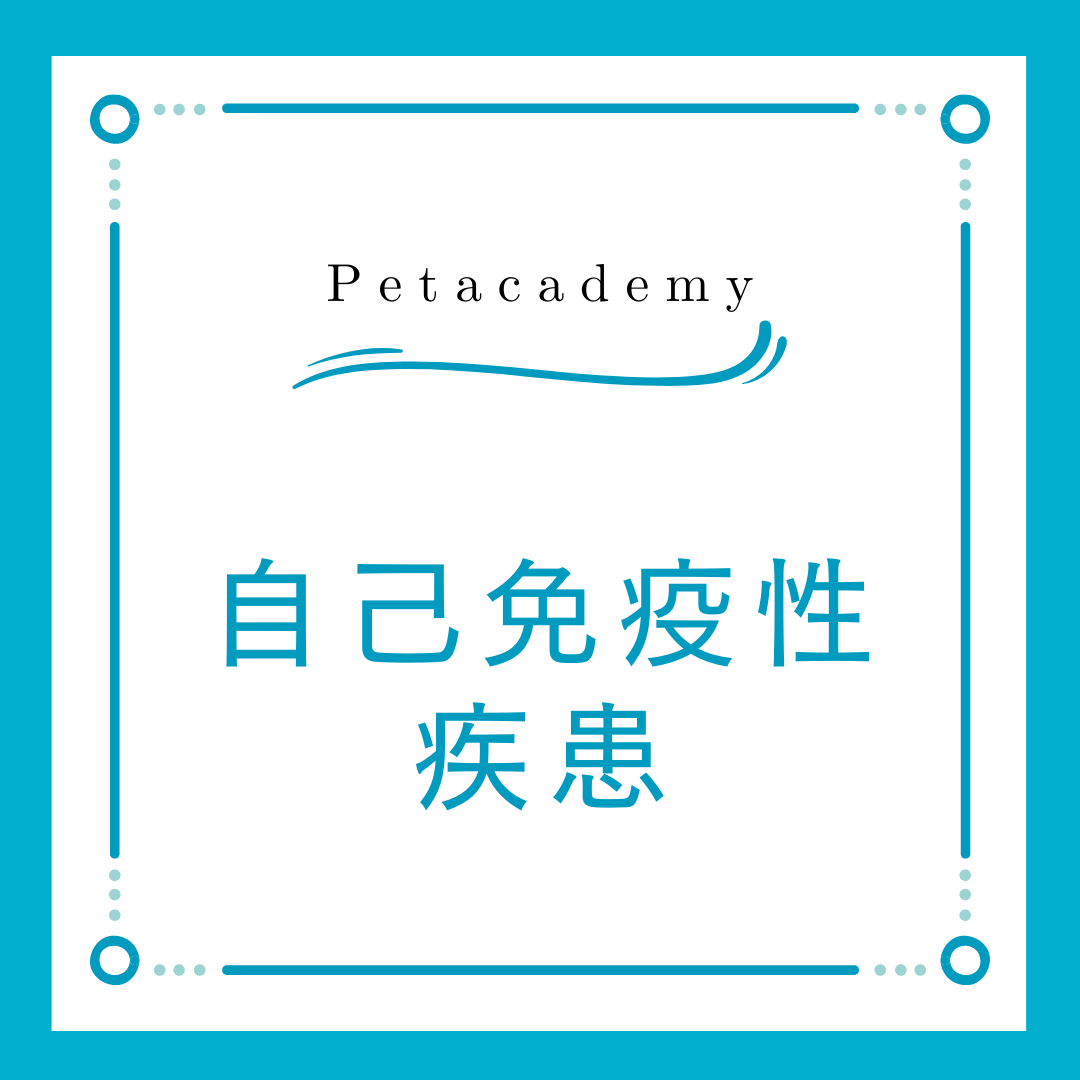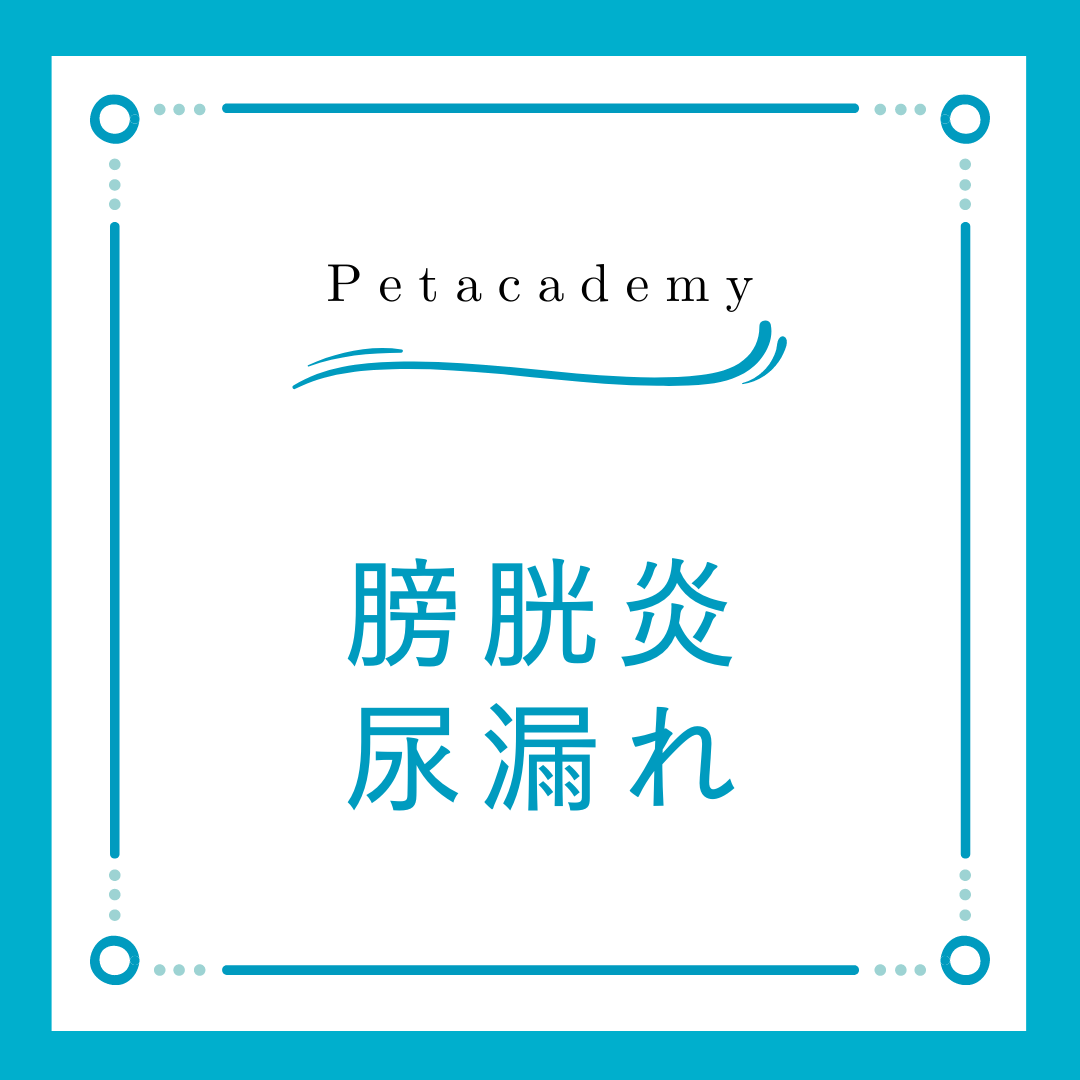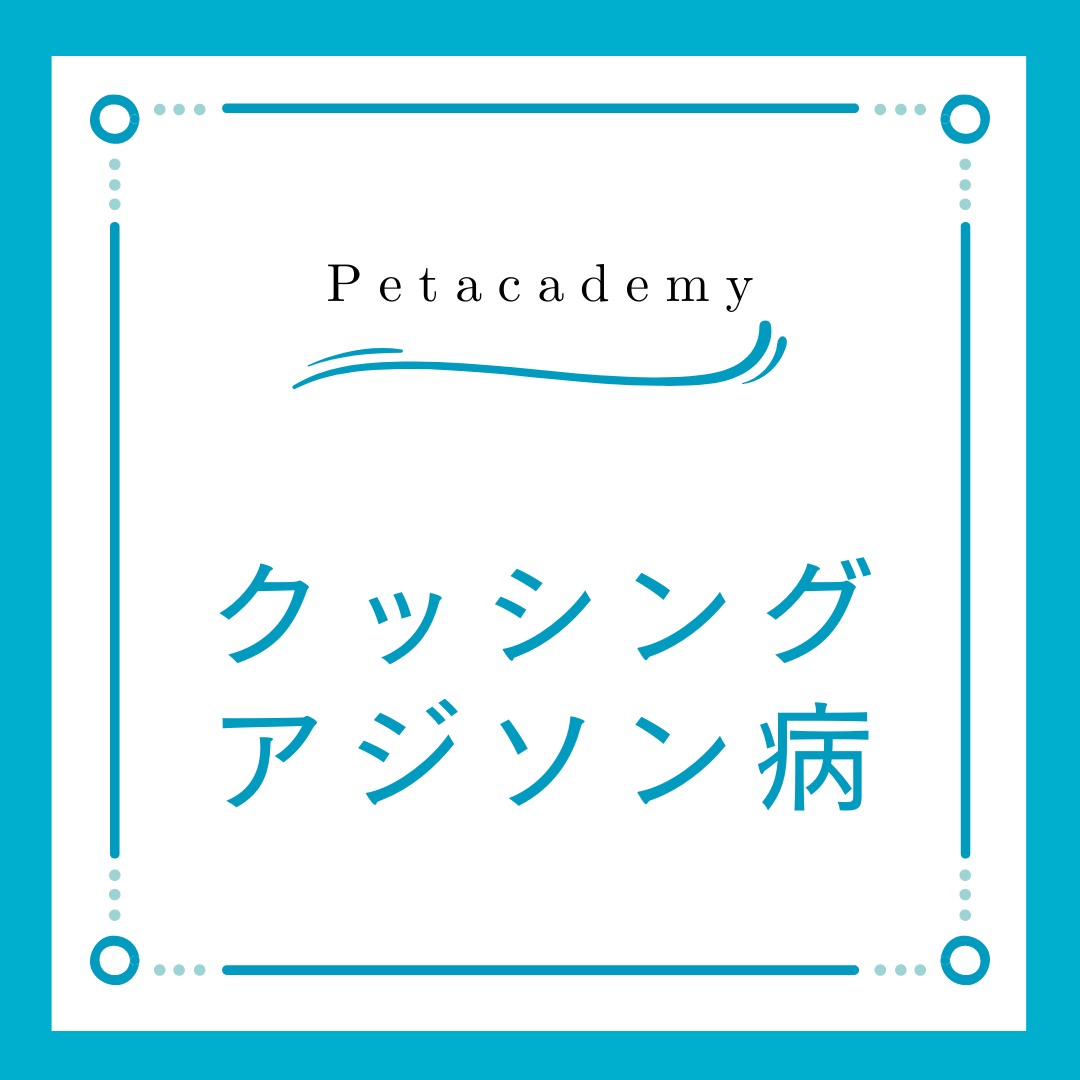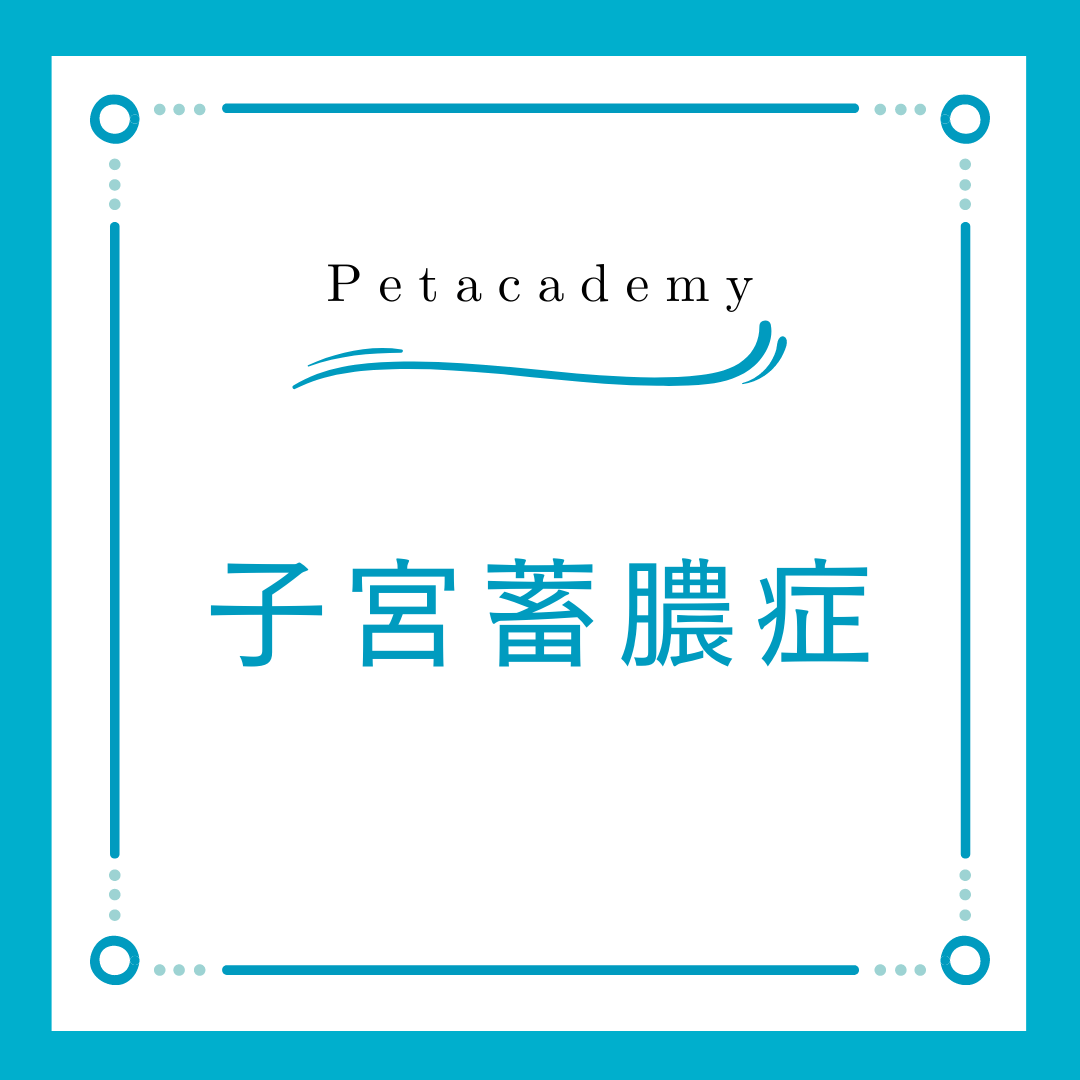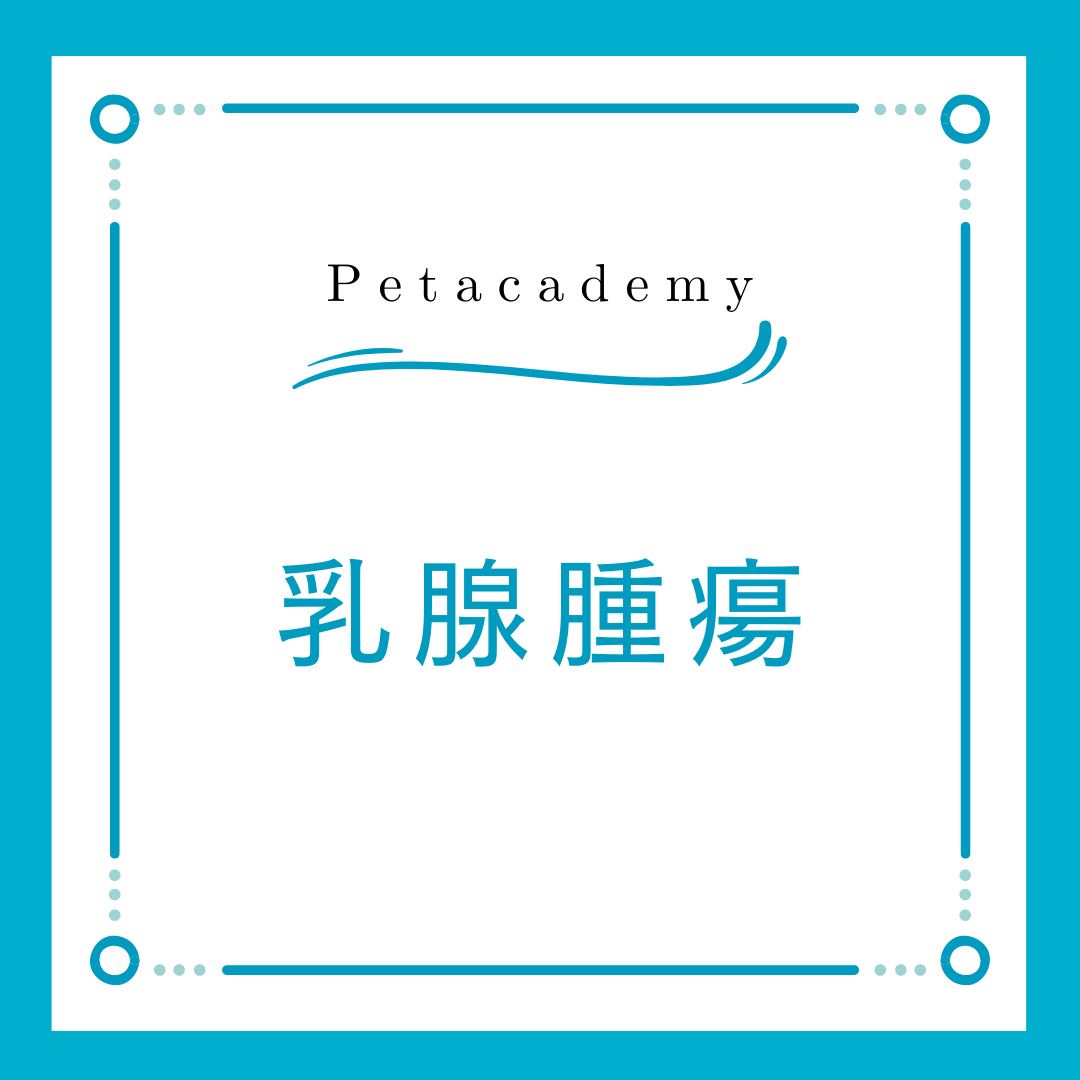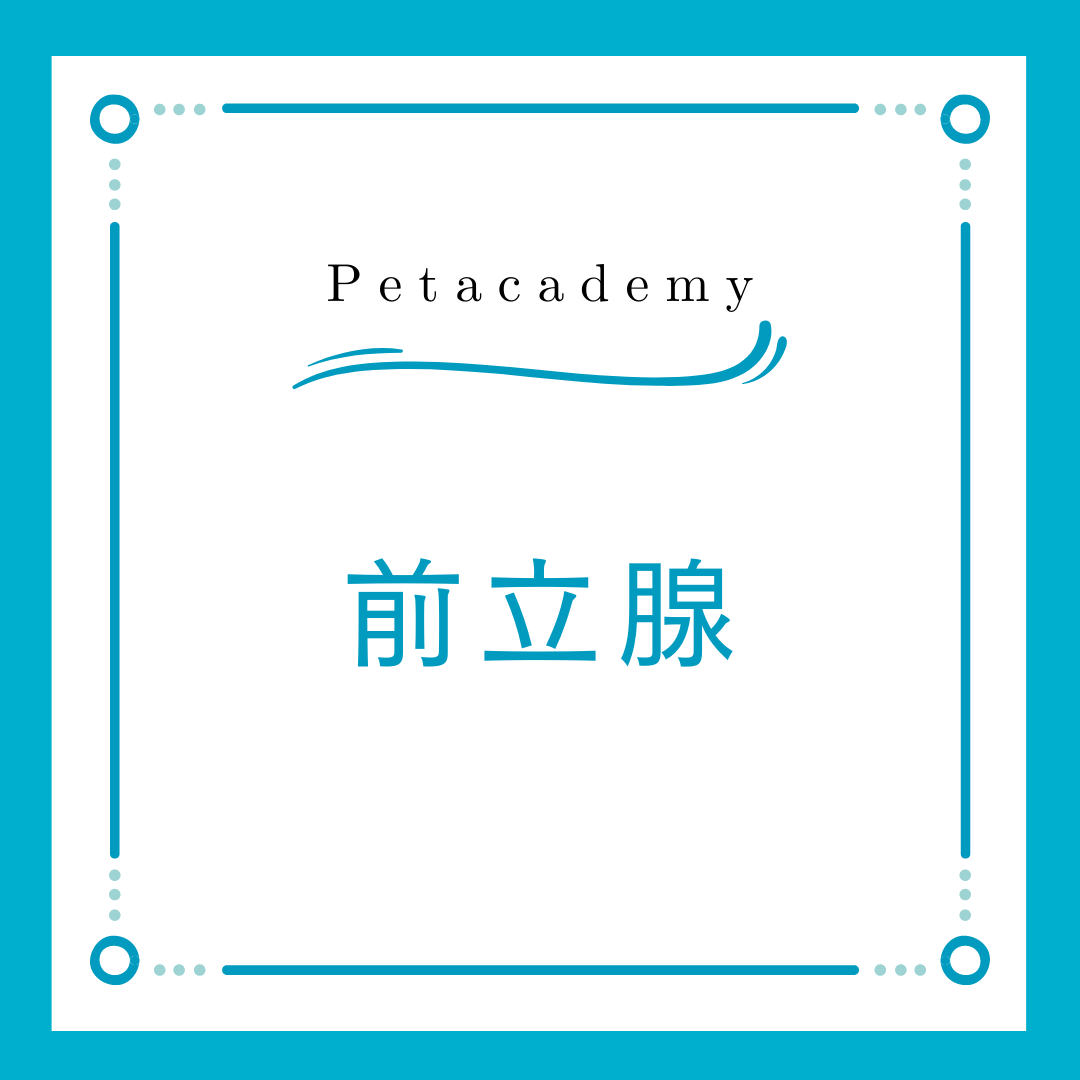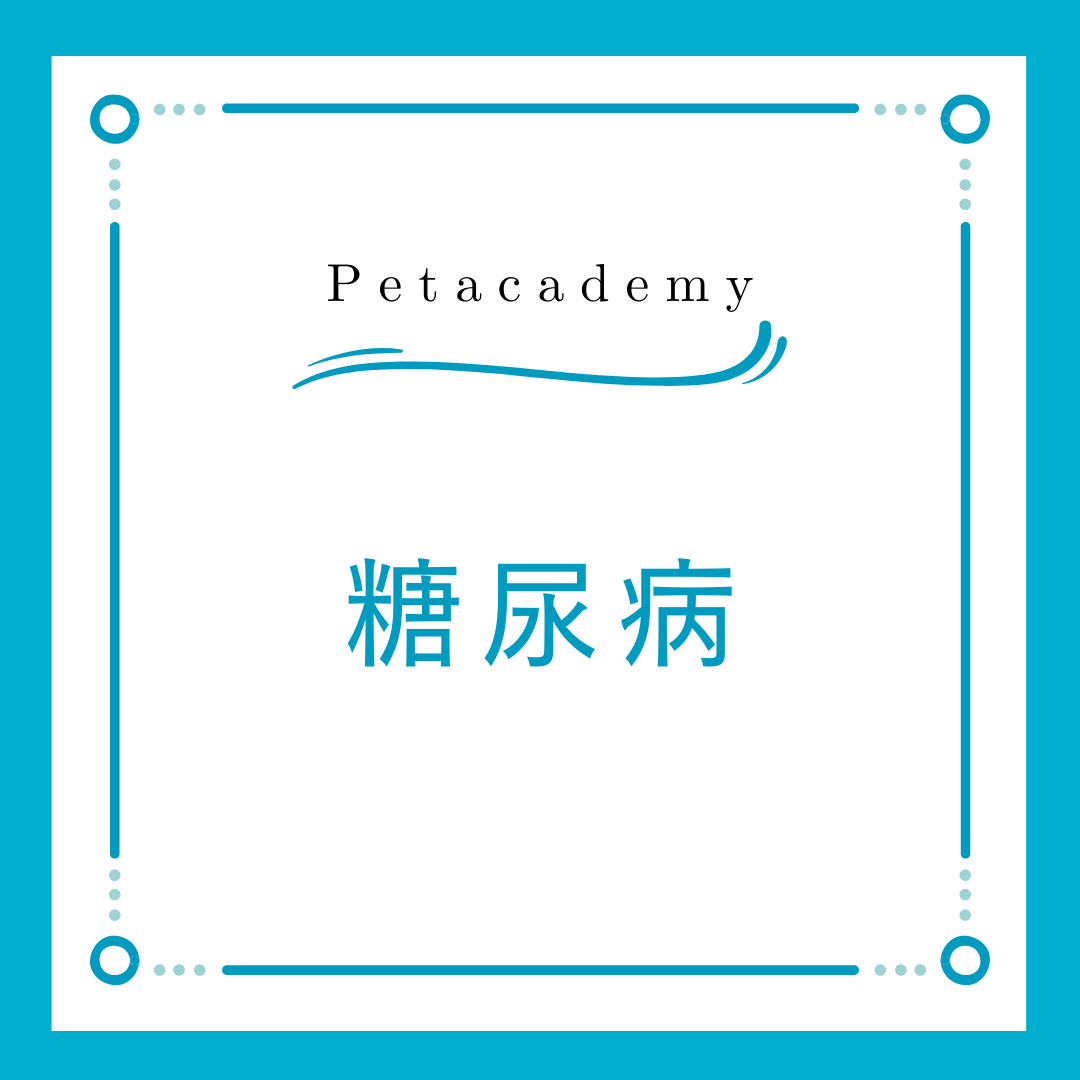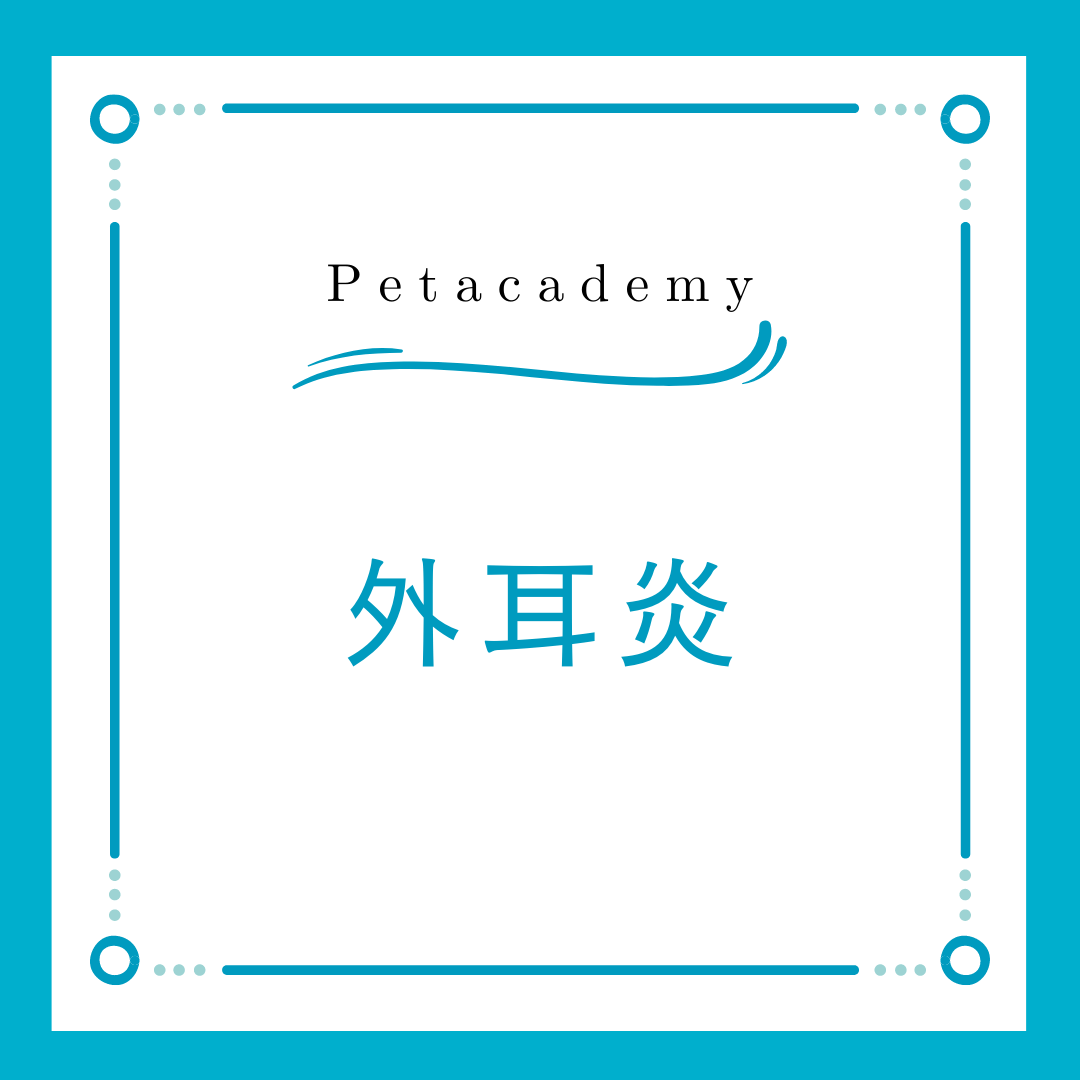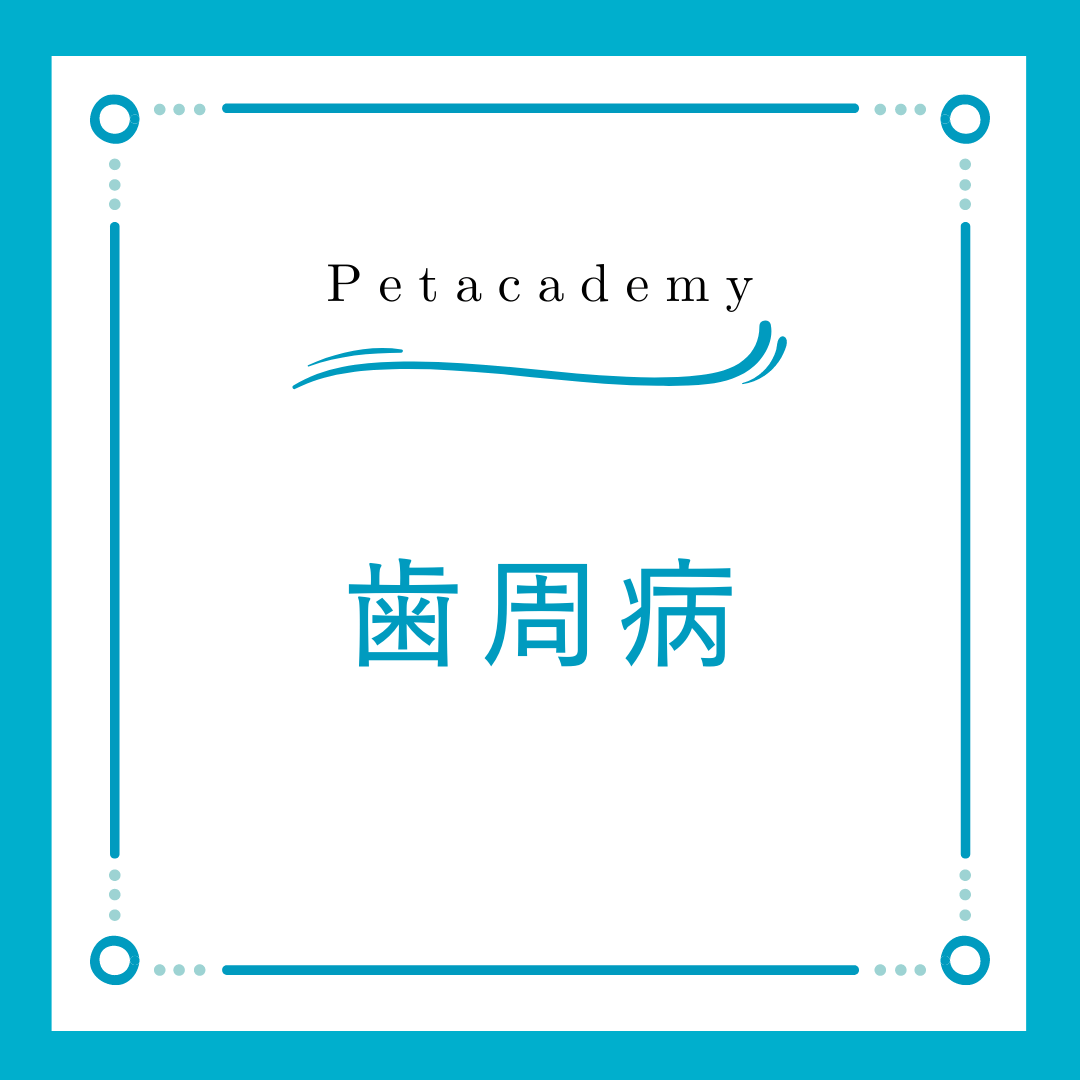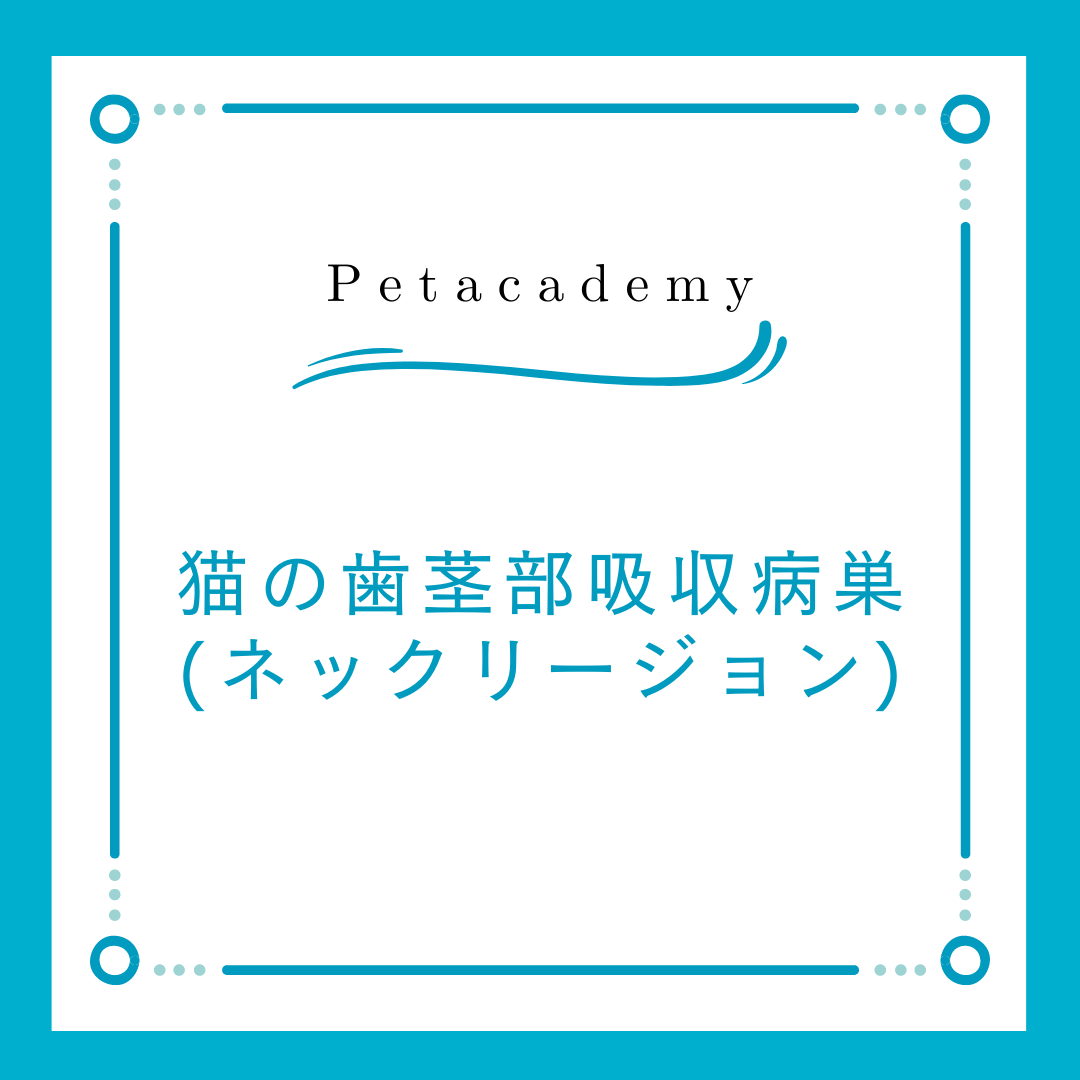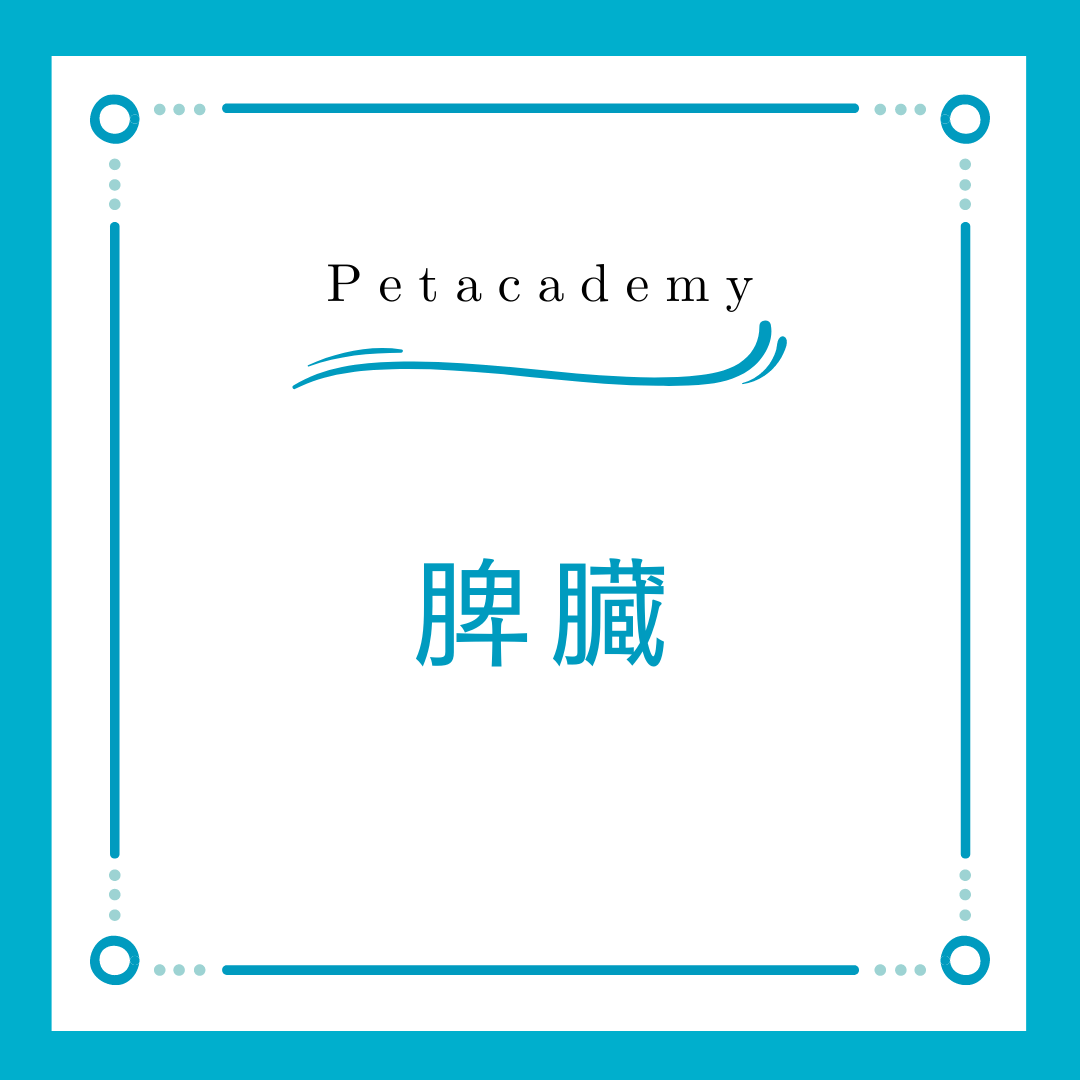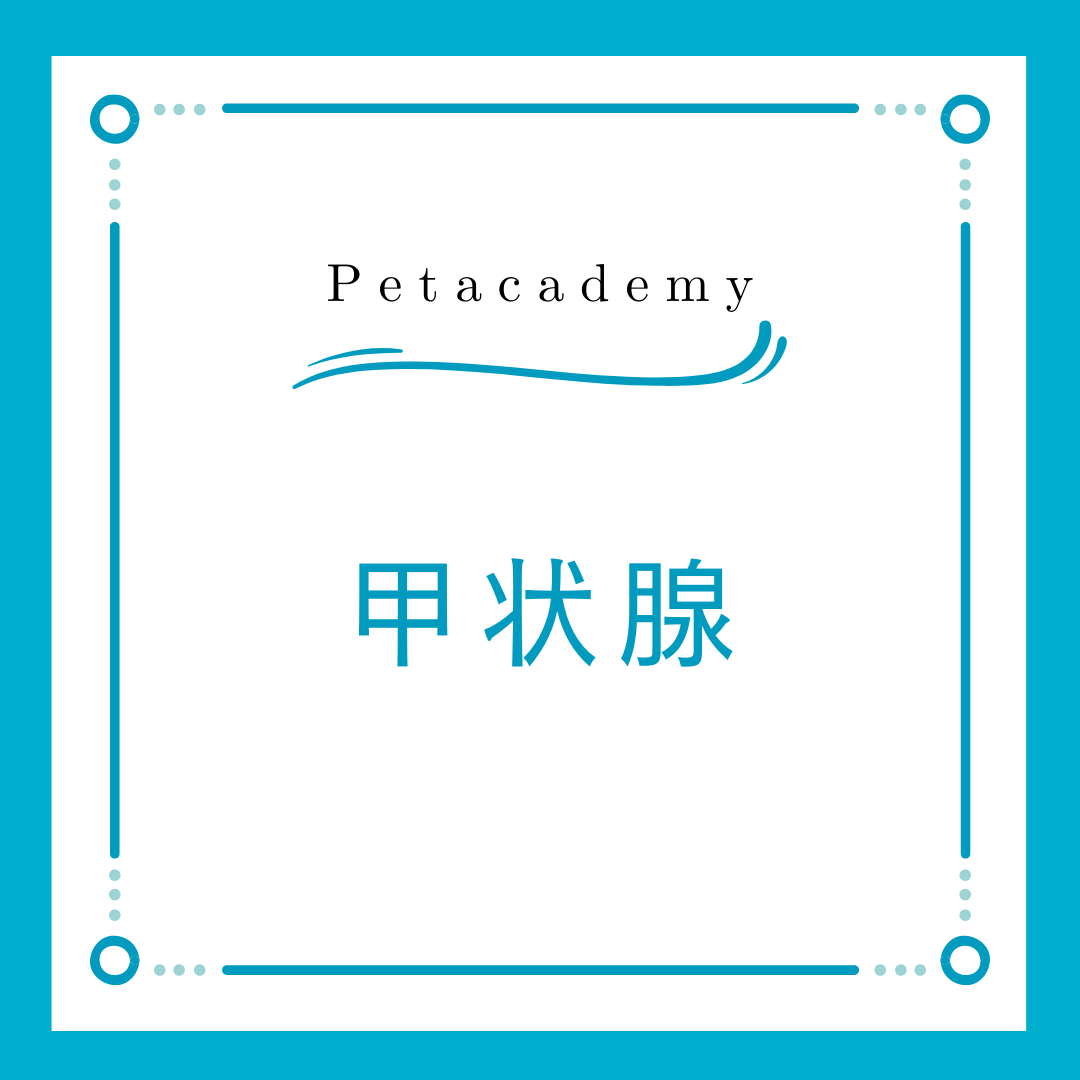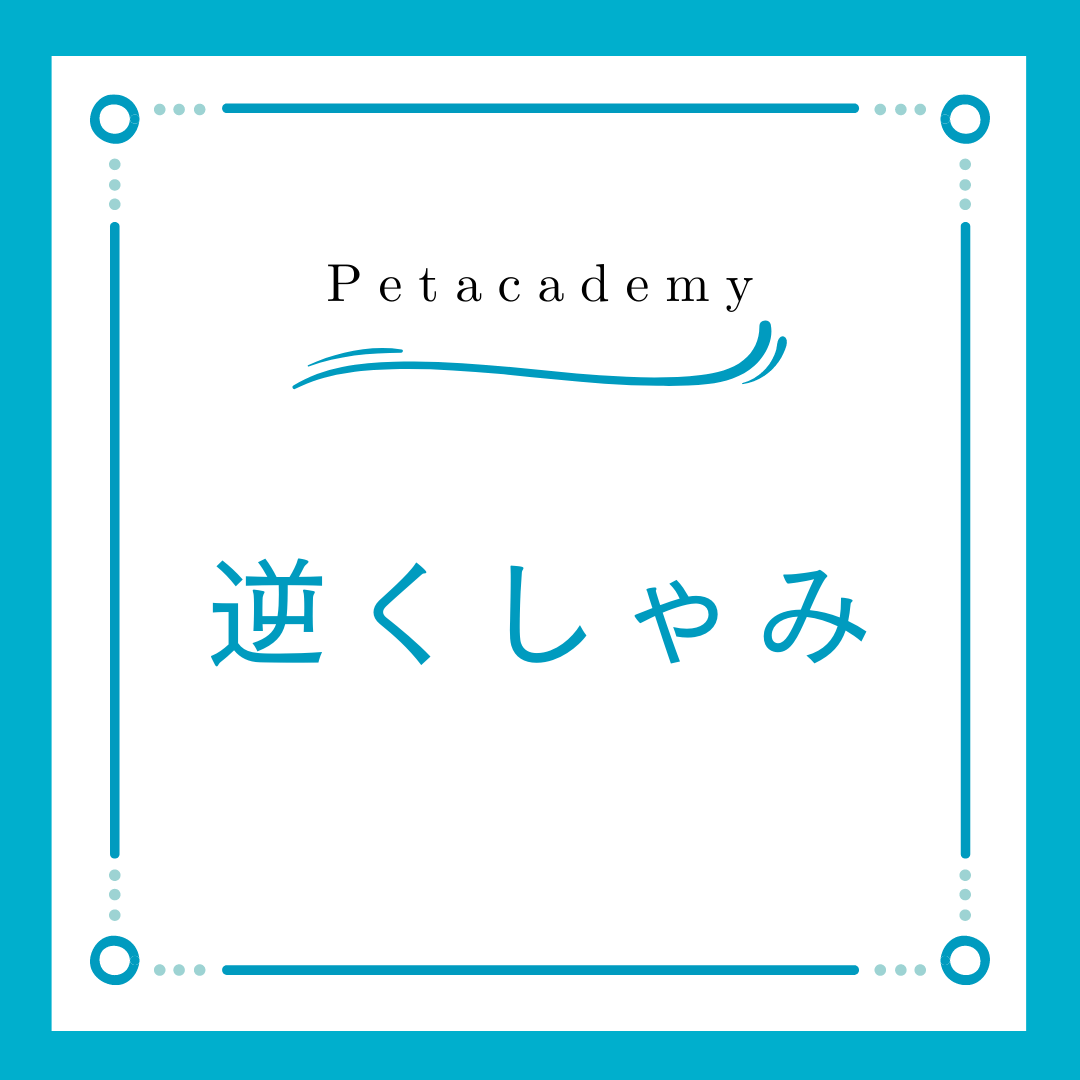お知らせ
2024年5月2日(木)〜5月7日(火)まで、誠に勝手ながらGW休業とさせて頂きます。
商品の配信設定につきましては、2024年5月1日(水)午前9時までに決済が完了したご注文に限らせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
3月1日以降はPC、スマホ、タブレットで学ぶ、配信(オンライン)教材販売のみとなります。
ペットアカデミー 「受講してのご感想」更新しました。
会員であれば、必要に応じてお好きなタイミングでマイページの購入履歴からダウンロード可能です。
ぜひご利用ください。
※注意事項
・非会員の方はマイページにログインできないため、ダウンロードはできません。
領収書の発行をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご依頼ください。
・マイページからのダウンロードは、発行から7日間有効です。
期間を過ぎた場合は、お問い合わせフォームよりご依頼ください。
〜大損をしたくない方のための情報への接し方〜
自分の頭で考え、自信を持って決断し、損をせず、望む結果を出せるようになるための「知的習慣」を身につけましょう!
詳しくはこちら
いつもペットアカデミーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
マイページに電子領収書をダウンロードするためのボタンが新たに設置され、期限内であればお客様のご都合に合わせて電子領収書の発行が可能になります。【2月下旬以降を予定】
機能が実装され次第、再度こちらのお知らせでご案内いたします。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
考える基準と情報の見分け方を学び、フード vs 手作りごはんを卒業しよう!
うまくいっている人には確認の場として。
努力が空回りしていると感じている方には改善点を探したり、見落としが無いかの確認の機会として…
ぜひ、本セミナーをご活用下さい。
詳しくはこちら
ペットアカデミー代表 須崎恭彦
2023年12月28日(木)〜2024年1月8日(月)まで誠に勝手ながら年末年始休業とさせて頂きます。
商品の発送、配信につきましては2023年12月27(水)am9:00までに決済が完了したご注文に限らせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
口内ケアセミナー2024
「自己流でやっているので、これで合っているのかどうか自信がない」という方
歯磨きセミナーを開催している方
復習・確認・伝え方のオプションとしてご活用ください
詳しくはこちら
考える基準と情報の見分け方を学び フード vs 手作りごはんを卒業しよう!
詳しくはこちら
須崎の放談会2023
治る子と治らない子は何が違うのか?
頑張る飼い主さんに後悔や罪悪感を持って欲しくないから開催します!
詳しくはこちら
2023年5月8日(月)発送分よりDVD教材の送料が変更されます。
16,500円(税込)以上ご購入の場合は引き続き送料無料でお届けいたします。
配信教材つきましては、送料無料で最短決済当日に配信可能ですので これを機に配信教材でのご購入をご検討ください。
詳しくはこちら
新着商品
正しいエビデンスのトリセツセミナー2024 ( 233分)
¥13,200(税込)
正しい?間違ってる?愛犬愛猫の食事セミナー (201分)
¥13,200(税込)
愛犬・愛猫の口内ケアセミナー2024 後悔しない!お口ケアの正しいやり方 (300分)
¥19,800(税込)
須崎の放談会2023 (188分)
¥13,200(税込)
皮膚のかゆみ対策と予防 諦めない犬猫の飼い主ができること 原因療法編 2022 (223分)
¥13,200(税込)
腎臓病対策と予防 諦めない犬猫の飼い主ができること_原因療法編2022 (500分)
¥22,000(税込)
おすすめ商品
配信教材:原因療法入門編 バイオレゾナンス法で ペットの病気の根本原因を探る (48分)
¥5,500(税込)
配信教材:とことんてんかんの話 - 脳だけに問題があるのか? - (63分)
¥11,000(税込)
配信教材:がんばる飼い主さんを応援する 犬猫の尿路結石症セミナー 2014 (166分)
¥13,200(税込)
世界でたった一つのプラズマ療法に取り組む動物病院 (90分)
¥13,200(税込)
Instagram